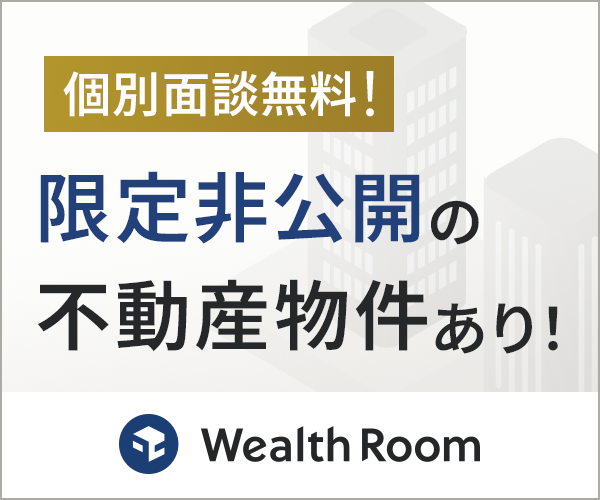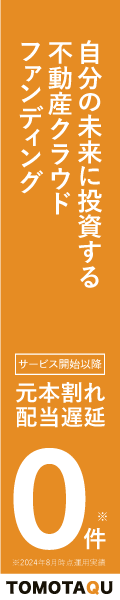セブン店長が過労で命を落とした コンプラ重視の時代に“心を壊す人”が増えているのは、なぜか
24時間営業で深夜勤務をするアルバイトが集まらない。そこで自らシフトに入るなどして6カ月間で1日も休みなく働いた末、重度のうつ病を発症。翌日、命を落としたという。
妻の訴えで労働基準監督署は調査を開始。店のオーナーは、彼の死は過重労働とは別の問題があったと主張したが、2024年11月に「労働災害」と認定された。
男性の「6カ月休みなし」という勤務時間データは、セブン本部にも送信されていたということで、労務管理はどうなっているかとマスコミが問い合わせたら、セブン&アイ・ホールディングス(以下、セブン&アイ)の広報は、「フランチャイズの個店にかかわる内容で、本部として答える立場にない」とピシャリ。これはFCビジネスの危機管理における定番回答で、要はこういうことを言っている。
「それってうちとFC契約している会社の労災でしょ? 亡くなった店長が休みしだったといわれても、それはその会社の問題であって、うちに文句を言ってくるのはお門違いですよ」
そういうFC本部側の本音も分からんでもない。ただ、この手の問題に多く関わった経験で言わせていただくと、もはやそういう「昭和の危機管理」が通用する時代ではない。筆者がセブン&アイの危機管理を手伝っていたら、ただただ企業イメージが悪くなるだけなので、こういう企業防御丸出しのマニュアル回答は控えるべきだと進言するだろう。
●本当にセブン&アイに責任はないのか
確かに法律的には「契約企業の不祥事」であることは事実だが、このセブン&アイの回答を「ですよね! 悪いのはブラックな契約先であって、セブンは巻き込まれただけでしょ」と支持できる人は少ないはずだ。
セブンのブランド、そして「24時間営業」というビジネスモデル下で発生した労働災害なのだから、無関係というのはさすがに無理がある。まずは哀悼の意を表して、契約企業で起きた事案とはいえ、FC本部としても重く受け止めていると伝えて、今後はフランチャイズオーナーとともに労働環境改善に努めていくくらいの姿勢を示すべきだ。特にセブン&アイにはそうすべき理由もある。
なぜかというと今、日本では「過労で心が壊れる人」が急速に増えているという深刻な問題があるからだ。
厚生労働省発表の「令和6年版 過労死等防止対策白書」によると、過労による精神障害で2023年に労災認定された人は883人。2022年より173人増加し、過去最多となった。このうち自殺または自殺未遂は79人だった。
「私たちは全ての活動にかかわる人の人権を尊重する」と表明しているセブン&アイは、2021年に「セブン&アイグループ人権方針」を定めている。これは自社の役員や従業員だけを対象したものではなく、「全てのビジネスパートナーに対しても本方針の支持を継続して働きかけ、協働して人権の尊重に取り組んでまいります」と高らかに宣言している。
それはつまり、セブンの38歳店長が6カ月間休みなしで働いた末、心が壊れて亡くなったことを「契約先の労災なんで関係ないっす」と他人面するのは、この人権方針が「うそ」だと認めてしまうことになるのだ。
●なぜ「過労で心が壊れる人」が増えているのか
さて、そんなセブン&アイの立場はさておき、「過労で心が壊れる人」が増えていると聞いて、モヤモヤしている人も多いはずだ。
コンプライアンス重視が叫ばれ、管理職が部下を注意する際にも心を傷つけないよう注意するのが当たり前の時代、心を病む人が減ったというなら理解できる。しかし、現実はコンプラを重視するほど「病む人」が増えているのだ。
実は、この理由は非常にシンプルだ。いくらコンプライアンスだダイバーシティだときれい事を並べたところで、日本企業の「ビジネスモデル」は基本的に何も変わっていないからだ。
稼ぎ方が変わらなければ、働き方も変わらない。むしろ、職場で新しいルールやスローガンが唱えられ、コンプライアンス研修が増えたことで「余計な業務」が増えている。現場で働く人の心と体がますます追い詰められているのだ。
「いやいや、さすがにそんなことはないだろ」と驚くかもしれないが、このあたりは38歳の店長が亡くなった大分のセブンを見ればよく分かる。
まず、大前提の事実として大分では若者の人口が急激に減少している。例えば令和2年(2020年)国勢調査における大分県の若年女性(20~39歳)人口は9.8万人。前回5年前の調査が11.4万人なのでガクンと減っている。もちろん、この傾向は男性も同じだし、他の世代も減っている。
若年層が万単位で減少している以上、バイトの確保が年々難しくなっているのは言うまでもない。そうなると「低賃金労働者」に依存するコンビニというビジネスモデルは、転換を余儀なくされるはずだ。具体的には店舗数の整理・統合を進めたり、営業時間を短縮したりするのだ。
しかし、残念ながら大分のセブンからは、そのような動きがあったことは読み取れない。
●38歳セブン店長が行っていたこと
若年女性が11.4万人いた2015年、大分県内のセブンは186店舗。そこから若年女性がガクンと減って9.8万人になった2020年も186店舗。そして、38歳の店長が亡くなった2022年も変わらない。
商圏内の人口が急速に減っているのだから、バイトもどんどん集まらなくなる。しかし、店舗の数がまったく変わらないということは、誰かが犠牲になって、何人分ものバイトの仕事を一手に引き受けているということだ。
ここまで言えばもうお分かりだろう。そう、亡くなった38歳店長のような人たちだ。彼らは「店舗数」と「24時間営業」を死守するため、店長業務をやりながらバイトの代わりに働き、1人で何役もこなしていた。心が壊れてしまうのも無理はない。
……という話をすると「でも、そういう無理な店舗運営をしていたのは大分のフランチャイズ側なんだから、やっぱり悪いのはそっちじゃない? セブン本部としても契約先のブラック労働是正まで介入できないだろ」というご意見もあるだろう。
ただ、セブン&アイのやっていることを冷静に見れば見るほど、「地方のブラック企業の労災に巻き込まれた被害者」とはならない。
「人口激減でも店舗数を増やし24時間営業も死守」というビジネスモデルを掲げて、現場に「勝ち目のない消耗戦」を強いている「大本営」は、ほかでもないセブン&アイだからだ。
●かつて批判が相次いでいたセブンの戦略
忘れている方も多いだろうが、セブンは今から6~7年前、「ドミナント戦略」(同一商圏内に多くの出店することで地域内のロイヤリティーを高める戦略)と「24時間営業」というビジネスモデルの根幹をなす2つの柱について、見直すべきではないかという指摘が相次いでいた。
きっかけは2019年2月、大阪にあるFC店のオーナーが、「深夜のアルバイトが集まらない」として、24時間営業をやめ、独自に19時間営業に切り替えたのだ。これに対し、本部が反発し、対立が起きた。そこからセブンの店長やバイトの「過重労働」が問題になり、経済産業省が「新たなコンビニのあり方検討会」を開催。こんな指摘が相次いだ。
「コンビニ全体の売り上げは増加傾向にあるものの、一店舗当たりの売り上げは頭打ちとなっており、店舗数拡大で利益を上げるビジネスモデルは転換点に。店舗間の競争が激化し、オーナーにとって厳しい経営環境が出現」(第1回 新たなコンビニのあり方検討会事務局説明資料より)
ちなみに手前味噌(みそ)で恐縮だが、筆者はこれ以前から以下のような記事で繰り返し、セブンにビジネスモデルの転換を勧めており、このままでいけば「壊滅的な危機」が訪れると予測していた。
・“変態セブン”が生まれた背景に、地獄のドミナント戦略(ITmedia ビジネスオンライン 2018年9月25日)
そして実際、2019年2月に「24時間営業問題」が火を吹いたことで予測が現実になったわけだが、ではセブン&アイがこの「危機」を受けて、これまでのビジネスモデルを転換したのかというと、まったくそんなことはない。
●増え続けるセブンの店舗数
ペースはやや落ち着いたが、セブンは2019年の店舗数2万955店舗から順調に店を増やし、大分の38歳店長が自殺をした2022年には2万1402店舗、2023年は2万1533店舗と、578店舗も増やしている。経産省の検討会による「店舗数拡大で利益を上げるビジネスモデルは転換点に」という指摘をガン無視した形だ。
ちなみに、日本の生産年齢人口(15~64歳)は2019年に7545万人。2023年には7395万人なので、神奈川県川崎市の人口とほぼ同じ150万人が消えている。
では、ここまで人が減っているのに、なぜセブンは「拡大戦略」を続けるのか。コンビニの評論家などは「生活者の活動時間が多様化している」とか「一つの店が地域に提供する価値が増えている」とか「ふわっ」とした話でこの状況を肯定するのだろうが、ミもフタもないことをいえば、「店舗数拡大で利益を上げるビジネスモデル」を変えることができないていないことに尽きる。
「24時間営業問題」やコロナ禍もあって、翌2020年の売り上げは大きく落ち込んで4兆8706億円に。そこから店舗数が増えていくのと同じく業績も右肩上がりで増えて、2023年には5兆3452億円とまでなっている。
企業というものは、右肩上がりで成長しなくてはいけない。人口減少で市場が縮小しているにもかかわらず、そこだけは「死守」しなくてはいけないとなると、これまで通りの「店舗数拡大で利益を上げる」に執着するしかないのだ。
これで成長は維持できるが、人口減少で「現場」の疲弊はすさまじくなってしまう。そうなると「大本営」がやるのは、「現場のブラック化」を見て見ぬふりをするしかない。
●「兵士の使い捨て」と同じ
地方のコンビニを支えるフランチャイズ企業やオーナーたちが、現場に対してこれまで3人でやっていた仕事を1人でやれと命じる。睡眠時間や休みを削って1人何役でもやってもらう。つまり、「現場が命を投げ出すことで圧倒的な劣勢をはね返せ」という精神主義に傾倒していくのだ。
これは日本型組織の「あるある」で太平洋戦争末期に、敗退続きの日本軍が急速にブラック化して「兵士を使い捨て」にした原因も基本的にはこれと同じだ。
会議室で「どうすれば成長できるのか」と悩んでいる人たちは、セブンの現場を疲弊させている気などはもちろんない。しかし、市場の環境が大きく変わっている中で、過去のビジネスモデルや戦略に執着するということは、現場に「勝ち目のない消耗戦」を強いることなので、結果として「使い捨て」にしてしまっているのだ。
セブン&アイの経営陣は、今回の店長の労災を「セブン&アイグループ人権方針」に則って、この方針に合う形で対処すべきではないか。そして同様の犠牲者を増やさないためにも、「現場を犠牲にした拡大戦略」からの勇気ある撤退を決断していただきたい。
(窪田順生)