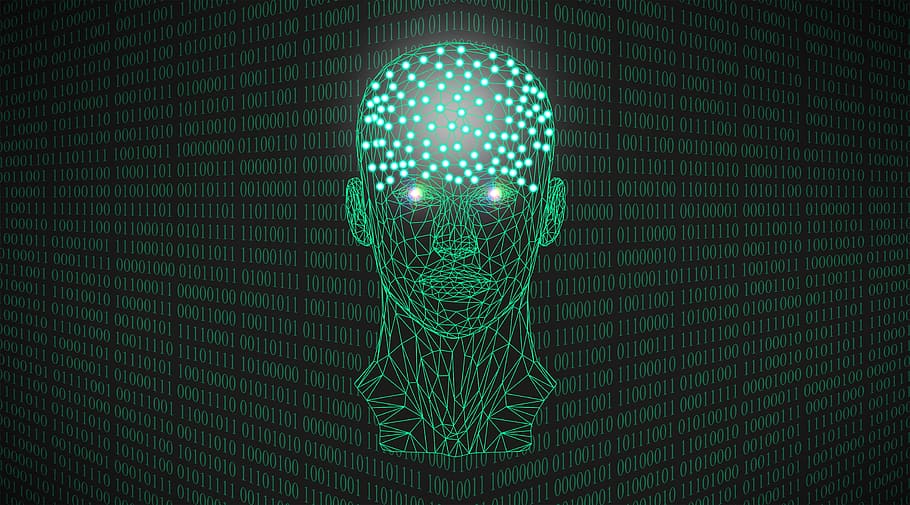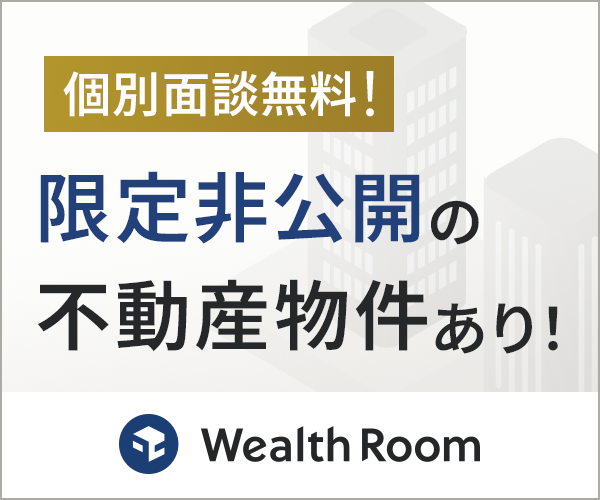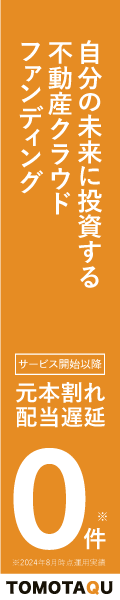ジブリ風、ディズニー風…生成AIは著作権侵害にあたる? “クリエイターの魂”=創作物をどう守るのか、専門家に聞いた
“罪悪感のない盗作”が問題視される可能性も
Q.生成Aを使って、特定の作風に仕上げた画像は著作権侵害に当たるのでしょうか?
永沼さん「まずは現在の法律論から整理しましょう。著作権法は『具体的な表現』を保護し、『作風』やアイデアそのものは原則保護の対象外です。例えば『森に住む丸っこい生きもの』というアイデアは問題になりにくいですが、『となりのトトロ』のトトロや、『魔女の宅急便』のキキと判別できるほどの描写をまねをすれば、著作権侵害の可能性が高まります。
つまり、『ジブリ風』『ディズニー風』といったテイストを似せるだけならセーフでも、具体的なキャラクターの容姿や構図をそっくりに描けばアウトになりかねません。
実際問題としてAI生成では『~の画風で描いて』と指示するだけで、驚くほど高精度な出力が得られることがありますが、現状、利用者が特に気にすべきは、その出力結果が既存作品とどこまで重なっているかです」
Q 自分のプロフィール写真や自画像を「似顔絵風」で似せた場合はどうなるのでしょうか。
永沼さん「自分自身の写真をAIでジブリ風やディズニー風に変換する行為は、上述のとおり、基本的には著作権の侵害にはあたりにくいと考えられます。なぜなら、著作権法が保護するのは『他人の著作物』であり、自分の肖像をベースに加工するだけなら問題が生じにくいためです。
ただし注意が必要なのは、例えば『あるキャラクターと見分けがつかないほどそっくりに見える』ような仕上がりになってしまった場合です。髪型・衣装・ポーズ・表情などが、既存のキャラクターを連想させるレベルにまで似ていれば、『翻案』として著作権侵害を問われる可能性があります。
さらに、生成AIでは『何に似せたか』を利用者自身が明確に意識していなくても、学習データの中に含まれていた既存作品の要素が知らず知らずのうちに再現されてしまうこともあります。この“無意識の模倣”が、『罪悪感のない盗作』を数多く生み出しているとして、社会的に問題視される可能性も否定できません」
Q 同人誌やファンアートといった、いわゆる二次創作はどうでしょうか。
永沼さん「同人誌やファンアートなどの二次創作は、原作者の許可なく行えば形式的には著作権侵害に該当します。しかし、日本ではファン文化の一部として黙認されるケースが多く、商業利用しない限り一定の範囲で許容されているのが事実だと思います。
ただし、今後、AIが一瞬で“ほぼ公式レベル”の作品を量産できるようになると、事情は変わってくるかもしれません。従来のように『人力による愛ある創作』とは異なり、「誰でも・簡単に・無数に』生成できる環境が整ってきたことで、著作権者が『これは見過ごせない』と判断する可能性もあります。
生成AIによる二次創作を個人的に楽しむ域を超え、出版化を狙う動きもあると聞きます。商用利用や大規模な拡散などは著作権侵害を問われるリスクも大きくなります。
実際に、一部の権利者は生成物の公開や利用に対してガイドラインを設ける動きを見せており、今後はAIによる二次創作に関しても権利者側から新たなルールが求められるようになるかもしれません」
Q 日本と海外で著作権の侵害による訴訟に違いはあるのでしょうか?
永沼さん「日本では、2018年の著作権法改正で『情報解析を目的とした複製』が合法化され、要件を満たすのであれば学習段階で著作物を取り込むこと自体はOKとされています。
しかし、米国やEUでは、AIの学習がフェアユース等に該当するかどうかが現在争われている段階です。判断基準が曖昧な中、AI開発企業が無許諾で著作物を学習に使用したとして、複数の訴訟も起きています。仮に海外の事案で『学習段階そのものが侵害』と判断されれば、日本国内で合法だった行為も該当国では制限されることになります。特にグローバルに活動するAI企業や利用者にとっては、大きな影響が出ると思われます。
そのような中、オープンAI をはじめとした多くのAI開発企業は、著作権侵害の責任は基本的にユーザーにあるという立場を取り、利用規約でも注意喚起を行っています。違反が続くユーザーに対してはアカウント停止などの対応を取る可能性も示しています。しかし、『どこまでが作風の利用で、どこからが著作権の侵害か』は極めて曖昧です。
AIと創作の“温度差”
周囲の関係者から話を聞いているという永沼さんは、AIがもたらす利便性と、クリエイターの魂とも言える創作物をどう守るのかについても力説してくれました。
私たち利用者は、「どこまでが作風の利用で、どこからが著作権の侵害か」の線引きを正しく理解し、創作物に対する敬意を持ってAIを活用できているでしょうか。アイデアなどの作風と創作的表現の線引きは個別事案ごとに判断されるのですが、利用者も「本当にこれはセーフなの?」と迷いながら使っているのが現実でしょう。「あの有名人が使っているから」「この会社は問題視していないようだ」といった憶測の中で、“なんとなく判断”をしているケースも少なくありません。
判断基準が見えづらい中、過去の作品の中から無断でアイデアや表現を取り込みながら、完全オリジナルに見えるアウトプットを高速で得られている構造は、確かに従来の著作権法が想定してきた“誠実な創作行為”とは異なるという見方もできます。結果だけを見れば、AIが描いたジブリ風イラストはそれなりの完成度を持ち、しばしば「作風だけをまねるならセーフ」と言われます。これをどう考えるべきかだと思います。
現在の著作権法の基になる考え方は、AIが大量に作品を学習・再構成・生成する時代を前提に設計されていません。例えば、人間の個々のクリエイターが「~の作風」を取り入れる場合、その学習や試行錯誤にも長い時間がかかりました。ですがAIは、瞬く間に膨大なパターンを出力します。
この技術環境の違いが、著作物の保護と利用可能性のバランスを“今は”崩しているように見えるのです。
生成AIの登場によって、私たちは人間による創作の自由と権利保護のバランスを再び問い直さなければならなくなりました。制度や裁判結果のアップデートを待つことも大切ですが、私たち一人一人のモラル意識も重要になってきます。
法の抜け穴を突くのではなく、クリエイターの命ともいえる作品に対し「これは本当にリスペクトを持った利用か?」と自問する姿勢が、AI時代における共存、それから新しい創作の倫理を形づくっていく鍵になると思います。
作品はクリエイターにとって“命”のような存在であり、AIが無許可で学習し、一瞬で模倣や量産を行う現実には時に不安や傷も伴います。法律には、技術の進歩や社会情勢の変化による人々のモラルが反映されることがあります。そのなか、私たちはAIの進歩を受け入れ、期待しながら、同時に「クリエイターをどれだけリスペクトしているか」という問いを真正面から考えるべき時期に来ているのかもしれません。
人間が「創る」という営み、そして文化の発展を支える著作権制度。新たな技術が登場する度に、その解釈が難しくなる局面は歴史上何度もありました。これからも利用者と創作者の双方を尊重しながら、より良いバランスを追求していきたいものです。
オリジナルを生み出す創作者、それを新たな表現へと発展させる人々、そしてAIを用いてパロディを楽しむ層と、それぞれの立場でそれぞれの視点があります。互いの利益を害さないようバランスを取ることが重要だという意識はある一方で、法的には「作風の模倣は自由」とされ、利用者の行為が強く許容されているようにも見えます。また、「法的に問題がないとしても、モラル的にどうなのか」「そもそもなぜ法的に許されているのか」といった疑問やジレンマを抱えている人も少なくありません。
かつて作風は時間と労力をかけて築き上げられたものであり、その背景には創作者の意志や個性が込められていました。しかし、AIによる模倣は一瞬で可能となり、その成果物が大量に拡散される中で、「創作の魂が切り貼りされるようだ」と感じるクリエイターもいます。この温度差こそが、創り手と使い手の間にある、見えにくい溝なのかもしれません。
オトナンサー編集部