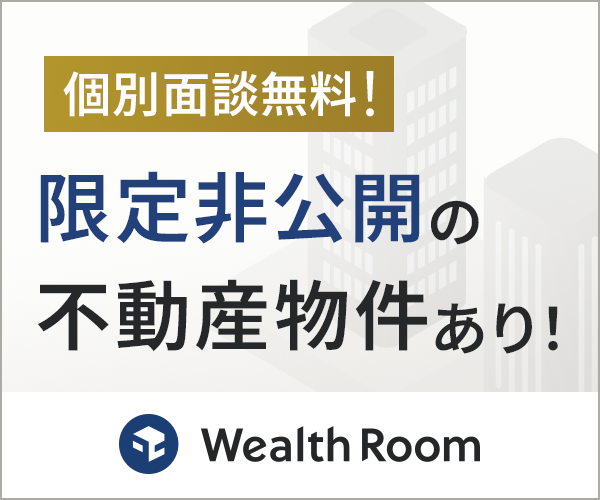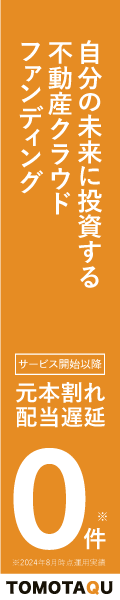地方が見捨てられる理由:能登復興の暗い現実
※本稿は、内田樹『沈む祖国を救うには』(マガジンハウス新書)の一部を再編集したものです。
■急速に進む地方の過疎化問題
首都圏に人が集まって過密化が進行し、他方地方では過疎化が急速に進んでいます。先日、能登半島で地震がありましたが、復興が進んでいません。なぜ、こんなに復興作業が遅れているのか。それは政府に「復興させる気がない」からです。
今回の激甚災害の被害は、少子高齢化で人口が減っている過疎地に集中しています。そのような過疎地に復興コストをかけるのは無駄だと考える人が政策決定にかかわっている。だから復興を意図的に遅らせている。
「高齢者は故郷に戻って、家を建て直し、生業を再開するだけの気力も体力もないから、遠からず仮設住宅にいるまま鬼籍に入る。そうなると、住民がほとんどいないような集落へ続く道を修復したり、そのためのライフラインを補修したりする必要はない」そういう考え方をしているのです。「健康で文化的な生活がしたかったら、都市部に引っ越せばいい。山の中の過疎の集落のために道路を通す、橋をかける、トンネルを通すとか、そんなところに予算を投じることはできない。行政コストの無駄遣いだ」、そういうことを公然と語る人もいます。
■江戸時代の人口は今よりはるかに少ない3000万人前後
多くの人がそれに反論できずにいる。コストとベネフィットというふうなビジネスの用語で語ると、「過疎地にはコストをかけない」ということは合理的な判断のように思えます。でも、これは明らかに言っていることがおかしい。「人口減」と言われますが、今でも日本列島には1億2500万人いるのです。
江戸時代の人口はだいたい3000万人前後で推移していました。276の藩があり、これらの藩は原理原則としてエネルギーと食料に関しては自給自足でした。それぞれの藩ごとに特産品があり、固有の文化があり、固有の技術があり、人々は伝統的な祭祀儀礼芸能を守っていた。人口3000万人の時に、全国津々浦々に人が暮らし、生業を営むことができたのです。それが人口1億2500万人では「人が少なすぎて」不可能になったと言われも、僕は納得できません。
■適切に資源を分散すれば人口5000万人でも暮らせる
でも、江戸時代より1億近く人口が多いのに、もはや地方には生業の拠点や固有の文化を発信する拠点など作れるはずがないと、多くの人が公言している。これはおかしくありませんか。江戸時代は3000万人、明治末でも5000万人です。その時代に「人口が足りないので、もう地方は棄てて、東京に集まるしかない」というようなことを言った政治家は一人もおりません。適切に資源を分散すれば人口5000万人まで減っても暮らせる。それは歴史的事実として検証済みなのです。
21世紀末に日本の人口は5000万人と予測されています。だったら、日本の人口が5000万人の時に、どういうふうな人口分布であったのか、それを参考にして制度設計は行われるべきだと僕は思いますが、なぜか、誰もそう言わない。ほとんどの人が首都圏に人が集まっていくのは自然過程であるかのように語る。まるで人口減は台風や地震のような災害で、人間にはコントロールできないものであるかのように。でも、違います。これは100%政治の問題です。人間の力で、人口の偏りは補正できます。現に前例があります。
■明治政府が行った「教育資源」の分散
明治政府が行ったことの中で、確実に評価していいことの一つは、高等教育の拠点を全国につくったことです。教育資源を東京に一極集中させないで、地方に分散した。これは明らかに政策的なものです。
帝国大学は、東京、京都、大阪、名古屋、仙台、札幌、福岡、台北、京城の9つがあります。見ればわかる通り全国に分散されています。旧制高校もそうです。旧制高校の配置を見ていると、明治政府の意図がだいたいわかります。
一高は東京です。でも次につくられた二高は仙台です。仙台は、戊辰(ぼしん)戦争のときの奥羽(おうう)越(えつ)列藩同盟の拠点です。明治政府に抗った賊軍の本拠地です。そこに2つ目の旧制高校を三高は京都、四高は前田藩ゆかりの金沢。五高は熊本、六高は岡山、七高造士館は鹿児島でした。西南戦争の逆賊の拠点です。八高が名古屋。そこで「ナンバースクール」は終わり、そのあとは弘前、松江、静岡、水戸、山形、高知などいわゆる「ネームスクール」19校ができます。
■教育拠点と医療拠点を全国に均等に設置
この教育資源の分散はあきらかに意図的なものです。逆賊の拠点だった仙台と鹿児島に高校をつくったことも、金沢、水戸、岡山といったかつての大藩に高校をつくったことも政治的配慮です。周知のように、公共事業の資源分散については、戊辰戦争の賊軍の藩に対して、明治政府はきわめて冷淡でした。東北新幹線が開通したのは、東海道新幹線開通の半世紀後であることからそれは知れます。でも、教育拠点と医療拠点については、全国に均等に設置するという明確な意志を感じます。これを僕は高く評価します。
今進められている教育拠点の一極集中政策は明治政府の政策とは正反対です。政府が教育資源の一極集中を主導しているとまでは言いませんが、放置していることは事実です。それを防ぐための手立てを何も講じていない。これを放置しておけば、韓国と同じように、若い人たちは首都圏にどんどん集まってきます。
■教育の拠点と医療の拠点があれば人は集まる
若い人が都市に惹きつけられるのは当たり前のことです。先端的な文化に触れられるし、経済活動も活発だし、雇用機会も多いし、競争が激しい。どの業種でも自分が「どれくらいにランクされるか」がわかる。都市は査定が正確なのです。だから、才能のある若い人が都市に引き寄せられるのは仕方がないことです。
そうであるならば政治にできるのは、人口の都市一極集中を抑制することです。資源を地方に分配することです。
明治政府がしたように、まず教育資源と医療資源の地方分散を進める。そして、「日本中どこに住んでも、医療と教育については心配する必要がない」という体制を整備する。地方にいても、十分質の高い高等教育が受けられる。しっかりした医療機関で受診できる。そういう環境をつくることは市場に丸投げしていては不可能ですけれども、政策的に進めることは可能です。そして、教育の拠点と医療の拠点をつくっておけば、人はそこに住み始める。
----------
神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長
1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。2011年、哲学と武道研究のための私塾「凱風館」を開設。著書に小林秀雄賞を受賞した『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)、新書大賞を受賞した『日本辺境論』(新潮新書)、『街場の親子論』(内田るんとの共著・中公新書ラクレ)など多数。
----------

 |
kikori
国交省に復興状況と見通しをまとめたものあるけど、被害が大きすぎて復旧に時間が掛かるという印象しか出てこないぞ。上下水道の完全復旧は令和10年になってるし。3、4m掘る作業を一帯でやるんだから時間掛かるのは当たり前。無いも知らない馬鹿が吠えてるだけですね。 |
 |
CC
乱立して生徒定員割れしてる教育拠点の整理どころか新設するんですか?やるにしても従事者が足りなくて既存の学校や病院すら喘いでる中どうやって人確保するんです?両方とも待遇改善より国民の意識改善から必要なレベルですけど。仮にそれ増やして、明治と同じ改革が現代で成立するとなぜ思うんです? |
 |
verlies
誰でも言えるような理想論だけじゃなく、現実にそれが立ち行かない切実な理由は何なのか、想像や噂ではなく証拠で示してほしいな。その上で現実的な打開策の一つでも示さないと、ただの居酒屋の愚痴と変わりない。 |
 |
黎黒(くろ)
東日本や能登に比べりゃ規模の小さい阪神淡路ですら「震災復興再開発事業完了宣言」まで 3 0 年である。あと「各個人の持ち物である家を勝手に政府が修繕・立て直し・片づけたら権利の侵害になる」ってこともしらないのか(撤去は比較的簡単な申請ですませてくれたが)水害もあったので、被災者が生活を立て直すことを優先、それが落ち着いてからだろ常識的に考えて。 |