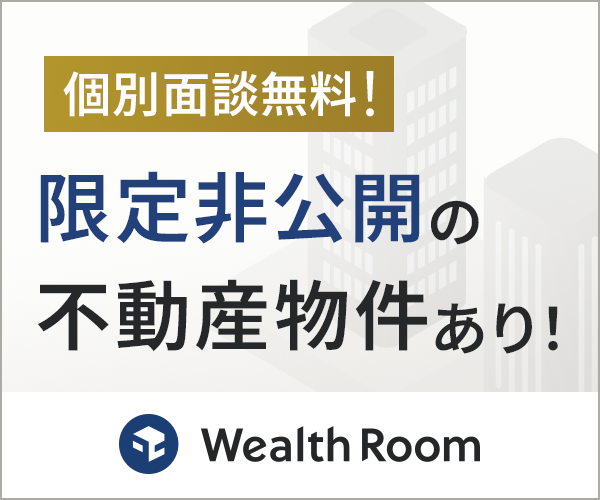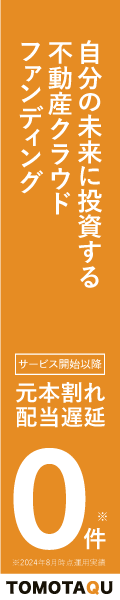アメリカ人の「トランプ離れ」は避けられない…株価を見捨て「安くて強いドル」を追求するトランプ政権の結末
■トランプ関税でドル高は進むのか
諸外国からの懸念にもかかわらず、意気揚々と「相互関税」の導入を発表した米国のドナルド・トランプ大統領。彼は今の米国経済を重症患者に例え、その快方のために必要な処方箋が相互関税だと説明する。トランプ大統領の解釈はともかくとして、マクロ経済的には、相互関税は米国経済にとって経済の強烈な緊縮策を意味するものである。
つまり、相互関税を課すことで、米国内に流通する輸入品の価格は上昇する。一方で、国産品の価格は下がらないのだから、米国のインフレは加速する。インフレが加速すれば実質所得が圧迫され、消費が下押しされる。輸入品の価格上昇コストを最終的に負担するのは米国の家計だし、マクロ的には、いわゆるインフレ税を納めることになる。
インフレを抑えるために米連銀(FRB)が利上げを行うことから、金融面からはドル高圧力が強まると期待される。また実需面からも、ドル高圧力が高まる。関税によって米国経済の成長の源泉である家計の消費が圧迫される一方で、貿易赤字の解消が進むと考えられるからだ。また輸入関税やインフレ税を通じて、財政赤字の解消も進むだろう。
足元の為替はドル安に振れているが、中長期的には金融と実需の両面でドル高圧力が高まり、ドル高になるという見解がある(図表1)。そうした見方も説得力を持つが、一方でトランプ流が続くうちは、米国経済の不確実性は高いままであり、ドル相場もそれに大きく左右される。それゆえに、一方向でのドル高は必ずしも望めないのではないか。
■ドル高是正に執着するトランプ大統領
当のトランプ大統領は、今のドル相場が高過ぎると主張してはばからない。国内の製造業を復活させるためには、ドル安でなければならないというわけだ。こうしたトランプ大統領の意向を受けて、就任直後に市場では、米国が主要国に対してドル安に向けた協調体制の構築を迫るという展開、いわゆる「プラザ合意2.0」の可能性が囁かれた。
しかし、トランプ大統領は相互関税を持ち出し、自ら国際協調体制を崩壊させている。したがって、国際協調によるドル安シナリオは、まず考えられなくなった。残る手段は、金融緩和を通じてドル安を演出することだ。実際にトランプ大統領は、FRBのジェローム・パウエル議長に対して、公然と利下げを要求するようになっている。
パウエル議長はトランプ大統領による要求を一蹴しているが、それでもトランプ大統領はパウエル議長に対して利下げを要求し、ドル安に向けた圧力をかけ続けるだろう。パウエル議長本人を解任できなくても、前回の任期と同様に、有形無形、そして様々な経路を通じて、トランプ大統領はFRBの金融政策に対して圧力をかけると予想される。
相互関税に加えてドル安まで追求するなら、米国景気は強烈に引き締められ、腰折れすることになる。確かに双子の赤字は劇的に改善するだろうが、当然ながらこの展開は、米国民一般に強い痛みを強いる。しかしトランプ大統領にとって重要なことは、あくまで自らの岩盤支持層に対するアピールであり、そうした人々はトランプ流を支持する。
製造業が実際に復活するかはさておき、ドル安という「追い風」を吹かすことが、政治的には重要なのだろう。まさに、政治の理屈が経済の原則を凌駕する悪例といえる。
■「安くて強いドル」は可能か
このように製造業の復活のために「安いドル」を求めるトランプ大統領だが、同時に基軸通貨としてのドルの位置づけを重視している。トランプ大統領と側近は、下野していた時期にドル以外の通貨で二国間貿易を行う国々に対する制裁措置を検討しており、実際にそうした国々に対して100%の輸入関税を課す方針を示していたことで知られる。
つまり、新興国を中心に緩やかに進む「ドル離れ」の動きを容認せず、ドルを国際決済通貨として使い続けるよう各国に要求しているのである。自らの理念に忠実なトランプ大統領は、場当たり的な規制を通じて、ドルの基軸通貨としての位置づけを保とうとしている。矛盾した表現だが、トランプ大統領は「安くて強いドル」を追求しているのだ。
しかし、トランプ大統領の場当たり的な経済運営は、基軸通貨としてのドルの信用力を傷つけるものばかりである。基軸通貨としての信用力は、必ずしも経済的な条件だけでは決まらない。米国が提供する世界的な警察力もまた、基軸通貨としてのドルの信用力の重要な源泉であるわけだが、トランプ大統領はそうした警察力の提供に消極的である。
抜群の流動性に支えられているドルの基軸通貨としての位置づけは、本来であればそう簡単には揺るがない。しかし、トランプ大統領による傍若無人な経済運営が続ければ、ロシアのウクライナ侵攻以降、新興国を中心に進んでいる「ドル離れ」の動きが、新興国ばかりではなく、今度は先進国でも加速することになるかもしれない。
現に、欧州の金融当局関係者は、市場の緊急時にFRBがドル資金を供給してくれるか疑念を抱いているようだ。FRBが供給に応じなければ市場でドル資金がひっ迫し、需給の観点からドルが暴騰する。しかし、直後に米国債の価格が暴落し、ドルも暴落しよう。戦略的にドル依存を減らしていかないと、欧州もその悪影響を強く被弾してしまう。
■トランプ流は持続可能なのか
ここまで悲観的な見解を述べてきたが、一方で、トランプ大統領によるインフレ醸成的な経済運営は持続可能なのか、という、素朴であるが本質的な疑問が湧いて出てくる。
先の大統領選で民主党から出馬したカマラ・ハリス元上院議員が敗北した大きな理由の1つは、ジョー・バイデン前大統領による物価対策の失敗にある。コロナショック後の急速な景気回復にもかかわらず、バイデン前大統領は景気対策を強化し続け、それが需要を膨張させ、急激な物価高を招いた。いわゆる「高圧経済路線」が失敗したわけだ。
物価高の抑制という米国民の期待を、トランプ大統領は裏切ることになる。これでは来年の中間選挙で共和党が大敗し、トリプルレッド(大統領、上下両院の多数を共和党が独占する状態)が崩れ、トランプ大統領を神輿に担いだ共和党の主流派たちの目論見も崩れる。それこそ、共和党内部で「トランプ降ろし」が進むことになるだろう。
最大の懸念は、共和党内でそうした自浄作用が働かないことだ。トランプ大統領はさておき、後継の指導者の中でトランプ流が根付くとすれば、米国のマクロ経済運営はいよいよ危うさを増してくる。それこそ、1971年のニクソンショック以来となる、国際通貨体制の在り方に地殻変動を伴うショックが世界経済を駆け巡ることになりかねない。
(寄稿はあくまで個人的見解であり、所属組織とは無関係です)
----------
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 副主任研究員
1981年生まれ。2005年一橋大学経済学部、06年同大学院経済学研究科修了。浜銀総合研究所を経て、12年三菱UFJリサーチ&コンサルティング入社。現在、調査部にて欧州経済の分析を担当。
----------