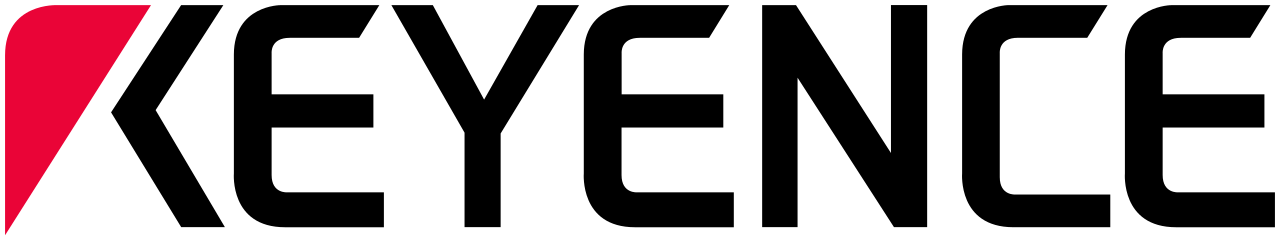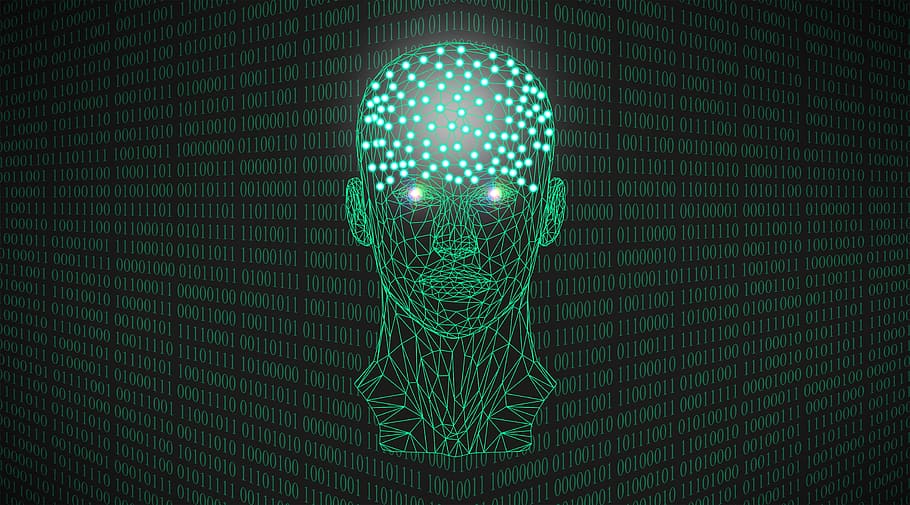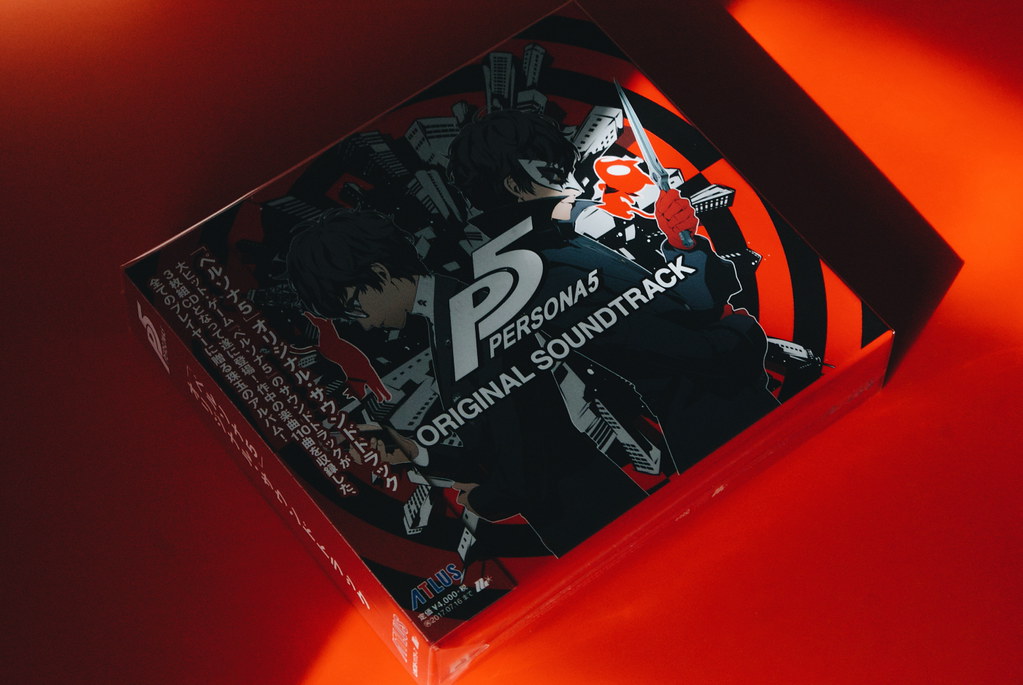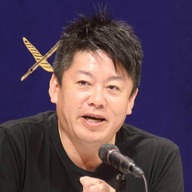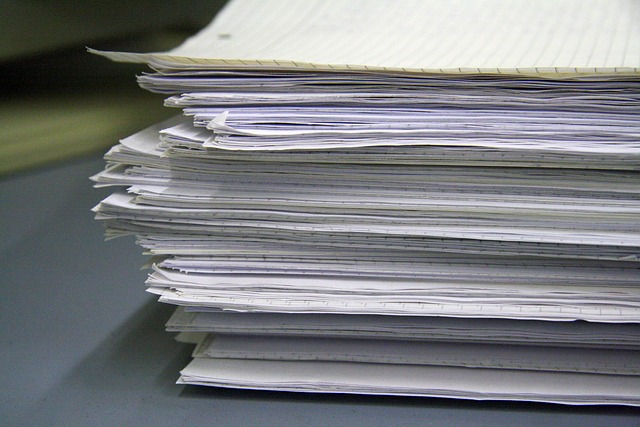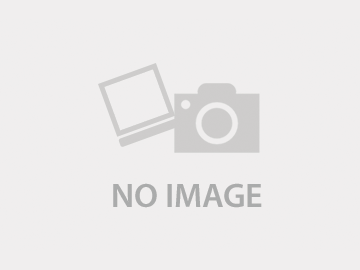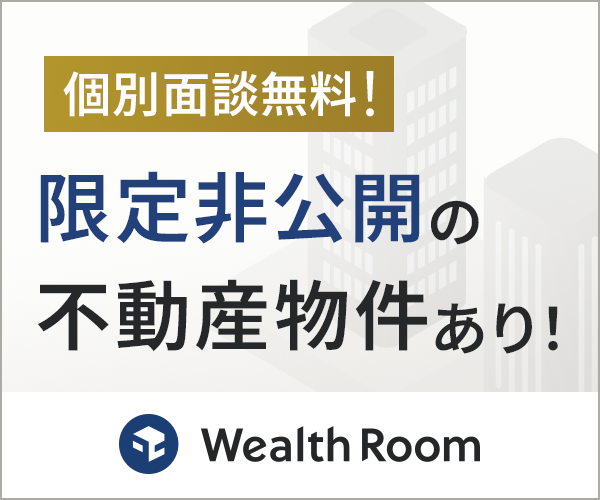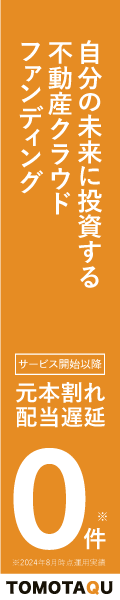「キーエンスはつんく♂である」創業から50年にわたり驚異の粗利益率80%を維持する製品企画力の源泉とは? | ニコニコニュース
今回は、創業以来、粗利益率80%を維持する超高収益企業キーエンスの価値創造の源泉を探る。
■ キーエンスは「つんく♂」である――世界の技術を演出
キーエンスには優れた技術があると思われますが、それだけで驚異的かつ長期にわたり持続されている高利益率を説明できるほどではないといえます。なにせ、創業来50年にわたり粗利益率80%を維持しているわけですから。
通常、これほどの利益率の場合、何かしらの特許(例えば医薬品)もしくは互換性(例えばマイクロソフトの製品)といった極めて高い参入障壁があるはずですが、それもありません。キーエンスの製品は高度とはいえ、他の企業でも作ろうと思えば作れるように思われます。
では、なぜキーエンスだけが驚異的な利益率なのか。筆者の理解は、キーエンスは「演出家」 であるからです。
例えば、レーザーセンサーの場合、重要な部品は半導体レーザーですが、半導体レーザーをキーエンスが製造しているわけではありません。重要なのはレーザーを使って「何をするのか?」なのです。
これは演出家に似ています。演出家は、物語、俳優、音楽、衣装などを統括し劇に昇華させます。最も重要なのは、「どんな物語を誰にどのような舞台でどのように演じてもらうか」という創造性なのです。
筆者は、20年ほど前に書いたレポートのタイトルを「キーエンスはつんく♂」としたことがあります。いまの若い人たちには過去にはやったグループかもしれませんが、「モーニング娘。」(や、秋元康氏によるグループ)は画期的なシステムでした。
それまで、アイドルといえば個人もしくは2人(ピンク・レディー)~3人(キャンディーズ)の編成で、かつ固定メンバーでした。対して、つんく♂さんや秋元さんは、多人数で構成され、かつ、メンバーが固定していないグループを提案したのです。当時、そうしたグループがこんなに成功すると思った人はどれほどいたでしょうか。
これら大規模グループの1人ひとりの魅力度合いは、他の芸能人と比較したときに際立って高いわけではないのですが、全体としては魅力的なものになっています。(冷徹にいえば)構成員は代替可能であり、演出家はその時々の需要に合った人をメンバーに迎えることで新鮮さを保つことができます。個々のメンバーよりも演出家のほうがリスクは小さいでしょうが、経済的な恩恵を最も享受しているのは演出家であるといえるでしょう。
若い世代の好みをつんく♂さんや秋元さんが理解するのと同様に、キーエンスにはソニーやトヨタ自動車の工場が何を求めているかを感じ取る感性、そして、自社および外部の技術を俯瞰して、その要望に応じる製品に昇華させる技能があるのです。
■ 顧客理解――どうやって作るか(how)ではなく、何を作るか(what)
前項から想像できるように、キーエンスを一般的な企業とは違うものにし、かつ、最も重要な工程は、(キーエンスの競争力は重層的なものであることを承知のうえであえていえば)製品企画力(顧客が求めているものの理解)といえるでしょう。
誇張していえば、同業他社が 「どうやって作るか」に頭を悩ませるのに対して、キーエンスは「何を作るか」 に重点を置いているのです。顧客の生産性に貢献できる製品を思いつく創造力、感性こそが、キーエンスの付加価値の源泉といえます。
その商品企画の「素」となるのが、営業です。顧客を知ることなく製品開発はできません。同社では営業組織が顧客ニーズの吸い上げを担っています。
制御機器業界に属する多くの企業においては、代理店経由の販売が販売額の多くを占めると思われます。一方、キーエンスは自社社員による直接販売です。顧客との接点を通して、ユーザーが抱える問題点を認識、企画・開発部門にフィードバックし、その課題に対する解決策を製品化する。
代理店経由の販売では、顧客のニーズへの反応がどうしても鈍くなってしまいます。逆にいえば、製品で差異化ができないために製造工程での差異化を余儀なくされている企業もあるかもしれません(申し上げるまでもなく、製造技術が付加価値の源泉である企業もあります)。
となると、誰もが思うのは、「同業他社も直接販売すればよいのでは?」ということでしょう。おっしゃる通りです。筆者もそのように進言していましたし、そもそも、筆者にいわれなくても同業の皆様もわかっていたと思います。しかし、できなかったのです12。
直販に切り替えようとすれば、既存の代理店網からの反発を招き占有率を大きく落としかねない懸念が大きかったと思われますし、また、自社で直販網を構築するのも簡単ではありません。しかし、徐々にキーエンスが大きくなるにつれ、危機感が出てきたのでしょう。
同業各社の妥協案は「自社の営業が代理店の営業と一緒に顧客訪問する」でした。しかし筆者は、それでは勝てないと思いました。費用の二重計上ですし、根本的な解決になっていません。
キーエンスと同様に、代理店経由販売が一般的な産業で直販によって競争力を獲得した他の事例を紹介します。ヒロセ電機・酒井氏の節でも紹介した未来工業です。
未来工業の手掛ける建設資材産業は一次問屋(10社)―― 二次問屋(3000社)―― 最終顧客という構造になっていて、一次問屋企業から「うちを使え」という要請(圧力?)が何度もあったそうですが、創業者の山田氏は断りました。200億円を一次問屋に販売すると約15%、30億円の手数料が発生する。
であれば、全国に社員を200人配置しても十分おつりがくるとして直接販売をし、それが、同産業での巨人・松下電工(現パナソニック)との差異化になったそうです。
一方、業種は違いますが、2024年9月20日付の「日本経済新聞」朝刊では、米国ナイキのジョン・ドナホーCEOの退任にあたって、同CEOが量販店を通さない直販を進めたことが占有率の低下につながったとしています。代理店活用と直販、どちらがよいのか一概にいえるものではありませんが、それは手法であり、重要なことは「顧客理解」であるといえます。
2「できなかった」と同時に「しなかった」ともいえるかもしれません。キーエンスの同業他社は同社をそれほど脅威だと認識していなかったように思います。30年ほど前、同業の1社の方に「キーエンスは脅威ではないですか?」とお聞きしたところ、「うちが負けるはずがない」との回答でした。
■ 高利益率――結果と同時に要因である
「利益率は結果」と認識されている方が多いと思われますが、「要因」ともいうことができます。なぜでしょうか?
キーエンスは「翌日配送」を競争力のひとつにしています。「それでは在庫負担が重いだろう」と考えますが、2024年3月末の「在庫(776億円)÷過去12か月の売上高(9673億円)」は29日分相当に過ぎません。どうしてこれほど少ない在庫で翌日配送ができるのか、と不思議になります。
理由は簡単です。売上原価/売上高比率(原価率)が17%と圧倒的に低いためなのです。「在庫(776億円)÷売上原価(1648億円)」は172日となり、実は6か月分相当の在庫を保有しているのです。そう、翌日配送に魔法のような仕掛けはないのです。
もし、原価率70%の企業が、キーエンスと同じように原価ベースで172日分の在庫を保有しようとすると、どうなるでしょうか? 売上高はキーエンスと同じとすると、3188億円の在庫を保有する必要があります!
在庫保有リスク(製品の陳腐化。年5%としても150億円)、在庫管理コスト(同1%とすると32億円)、金利負担(同1%なら32億円、2%なら64億円)などなど、300億円程度のコストがかかるでしょう。
同時に、債権回収リスクも減少します。いうまでもなく、原価率17%の債権未回収リスクは原価率70%の企業よりもはるかに小さく、さらにその差は広がります。自己言及パラドックスのようですが、利益率が高い(原価率が低い)は結果であると同時に要因でもあるのです。
<連載ラインアップ>
■第1回 「僕はギャンブラー」祖業の抵抗器から半導体事業へ転換して大勝ちした、ローム創業者・佐藤研一郎氏の勝負眼とは?
■第2回 虎の子の設計図を完全開示「競争を楽しむ」が信条のマブチモーター創業者・馬渕隆一氏の非凡人的な発想の原点とは?
■第3回 破綻寸前のルネサス エレクトロニクスを奇跡の復活へと導いた「最後の男」作田久男氏が修羅場で見せた胆力とは?
■第4回 「キーエンスはつんく♂である」創業から50年にわたり驚異の粗利益率80%を維持する製品企画力の源泉とは?(本稿)
■第5回 「ブラック・スワン」を見逃さない ジョンソン・エンド・ジョンソンが新事業の使い捨てコンタクトで成功できた理由
■第6回 20年間停滞し続けたミネベアミツミ、中興の祖・貝沼由久氏はいかにして業績5倍に成長させたのか?(4月1日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
虎の子の設計図を完全開示「競争を楽しむ」が信条のマブチモーター創業者・馬渕隆一氏の非凡人的な発想の原点とは?
破綻寸前のルネサス エレクトロニクスを奇跡の復活へと導いた「最後の男」作田久男氏が修羅場で見せた胆力とは?