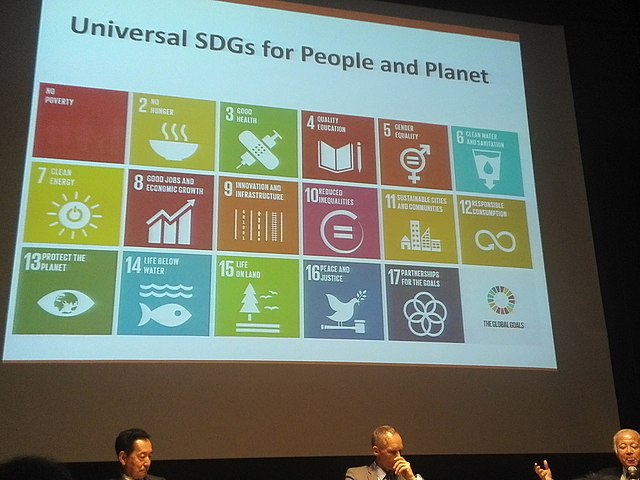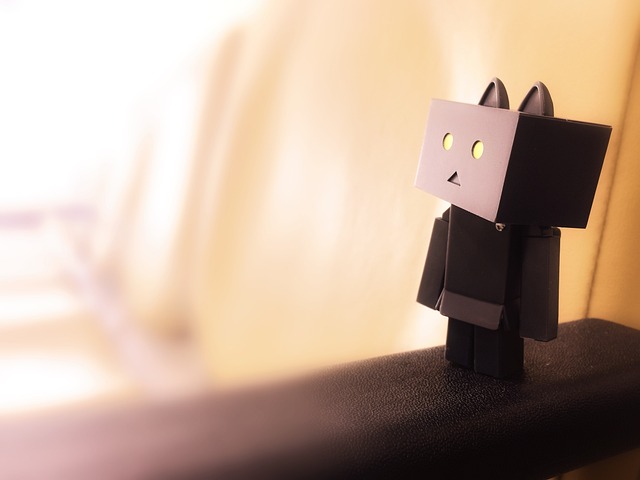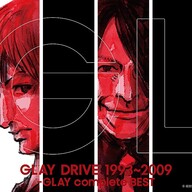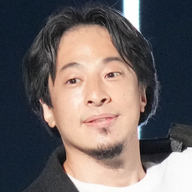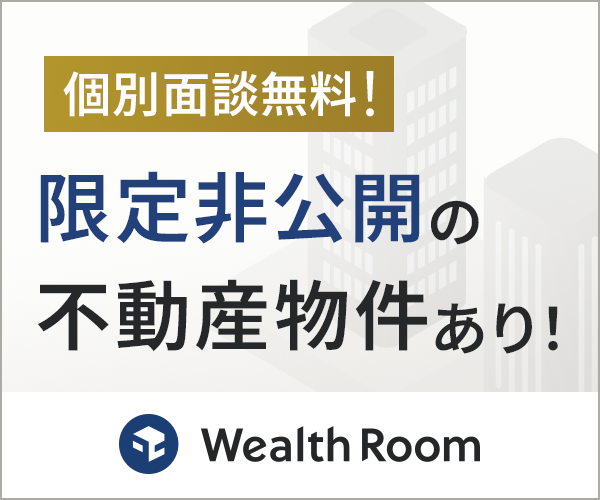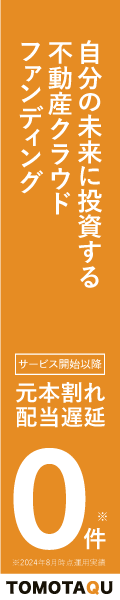皇室が「悠仁天皇だけになる」よりマシだけど…「旧宮家を養子に迎える案」で起こり得る「憲政史上初の異常事態」 | ニコニコニュース
■「旧宮家」からの養子案
令和7(2025)年3月10日、衆議院議長公邸に各政党・各会派の代表者たちが集まった。旧宮家の男系男子を「安定的な皇位継承」確保のために養子に迎えるという案をめぐって、協議の場が持たれたのである。
旧宮家の皇籍復帰案に対しては、民間人として長く過ごしてきたことから、国民に受け入れられにくいのではないかと懸念する声もある。
政府の有識者会議が「養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることが考えられます」と過渡的措置を提案しているのも、そうした意見への配慮に他ならない。継承資格を認めるのは復帰後に生まれてくる子世代からにしようというわけである。
皇籍復帰に前向きな勢力には自由民主党、公明党、国民民主党、日本維新の会などがあるが、3月10日に衆参両院が公開した資料によると、これらの党も継承資格を認めないという方向でおおむね一致している。実現するとしても、やはり継承資格が即時与えられることはないだろう。
さて、継承資格を与えないということは、万一その系統に皇位が移ることになってしまった際には、憲政史上初めての状況が生じる可能性がある。すなわち、一代飛ばすことによって、今まで登場する余地のなかった「天皇の父親」たる皇族が現れるという事態だ。
養子に継承資格を持たせないことを前提に議論するのであれば、まともに考慮されてこなかった皇父という存在について再検討したほうがよいだろう。
■「天皇の父親」が悩みの種に…
天皇の父親がどんな待遇を受けるかを考えるにあたっては、現行法上、天皇の母親が必ずしも「皇太后」になられるとは限らないことが参考になる。
戦前に書かれたものではあるが、宮内省図書寮編修課長などを歴任した歴史学者・芝葛盛(かずもり)による皇太后の解説を次に示そう。
「現制に於ては皇太后は天皇の御母を云ひ、皇太孫若しくは支系の皇族の天位を継がれたる場合には先帝の皇后を云ひ、陛下の敬称を奉る。(中略)往時に於ける尊称、追贈のことは行はれない」――国史研究会編『岩波講座日本歴史第10巻皇室制度』(岩波書店、昭和9年)47頁。
皇太孫や傍系皇族が即位された場合には、新帝の母親ではなく先帝の皇后が皇太后になられるという。この仕組みが今日まで引き継がれているのである。
現皇室典範は「王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする(※第7条)」と定めているが、母親には考慮を払っていない。それゆえに、皇母といえども親王妃どころか王妃にすぎない場合さえありえる。
このことから類推すれば、天皇の父親も同じように、親王もしくは王のまま留め置かれるとみるべきだ。
しかし、本当に一般皇族として扱われるのであれば、将来その存在が宮内庁の悩みの種となってしまうこともあるかもしれない。
■「デンマーク王配」の二の舞は避けたい
宮中における席次や歩く順序は、旧皇族身位令に準じており、「親王、王ノ班位ハ皇位継承ノ順序ニ従フ(※第2条)」とされる。したがって、継承資格がない天皇の父親は、皇室内でもかなり低い地位に置かれることになるはずだ。
ここで思い出されるのが、前デンマーク女王マルグレーテ2世の夫君、故ヘンリック王配――自身の待遇の悪さをしばしば訴えてマスコミを賑わせた――である。
2002年1月、全デンマーク国民を驚かせる事件が発生した。新年恒例の宮中晩餐会が催され、療養中の女王に代わって王太子(※現フレゼリク10世)が接遇したのだが、この時に息子よりも地位が低いことを思い知ったヘンリックが、ショックから数週間にわたりフランスの城館に逃避してしまったのである。
ヘンリックは当時、マスコミの前で次のように不満を爆発させている。「父親は誰もが自分の家の主人になりたがるものです」
■迎え入れる「養子」の待遇には慎重を期すべき
なお、英国王室の故エディンバラ公爵フィリップも、妻エリザベス2世の即位前には「自分の家ではボスでいられる」ことを願っていたという。ヨーロッパの王配と皇父とでは立場が違うものの、日本でも類似の騒動が起きる可能性はけっして否定できまい。
むしろ、自らも皇統に連なることへの誇りがあるであろう皇父のほうが、より強く不満を抱かれるかもしれない。「上古より、帝王の父として、無品親王にて果てたる例」はない――室町時代に後花園天皇の父・伏見宮貞成(さだふさ)親王がそう書いて尊号宣下を切望した前例もある(『椿葉記』)。
最高位者たる天皇はともかくとして、その他の子や孫たちよりも軽んじられ続けたならば、不満の一つくらいお抱きになっても不思議ではない。この一点だけを考えても、待遇には再考の余地があるはずだ。
■皇室への誹謗中傷にはどう対応するのか
何よりも問題だと思われるのが、裁判に関する取り扱いである。
秋篠宮ご一家への誹謗中傷が何年も続いている現状からするとほとんど知られていないのではないかと思わざるをえないが、まず大前提として、皇室の方々とて名誉毀損には法的措置を取ることができる。
一般皇族の場合はご自身で告訴することが想定されているが、刑法第232条の規定により「天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣」に限っては、内閣総理大臣が代わって行うことになっている。
なぜ皇室の中でも一部の方だけが特別扱いされるのか。天皇については、「国民統合の象徴」であるがゆえに国民を訴えることを期待できない――といった理由が挙げられている。
そして三后と皇嗣については、その天皇に極めて身近な存在であるため、国民を訴えることが同じく非現実的だからだとされる。
「天皇の極(ご)く身近の方でありまするので、天皇に国民に対する告訴を期待し難いと同様に、これらの方々も国民に対して告訴するというようなことは到底考えることができません」――司法次官・佐藤藤佐(とうすけ)(参議院司法委員会、昭和22年10月7日)
■皇室に「裁判沙汰」は持ち込みたくない
刑法第232条は、名誉を毀損されたご本人の「意思いかんにかかわらず告訴権を行使する」ことを前提としている。裁判結果について、天皇や皇族方に責任を一切負わせないためだ。
また、告訴権者については、皇室会議議長や宮内府長官なども検討されたものの、天皇との距離が近すぎるという理由から却下された。皇室会議議長の場合は、首相が務めるものだから本質は変わらないのだが、イメージ的にも遠ざけることが好ましいと判断されたのだろう。
「皇族会議の議長というようなものに告訴権を行使させた方がよいのじやないかということを一応考えて見たのでございましたけれども、併(しか)しそれでは余りに先程申上げました観点から、天皇に身近である」――政府委員・国宗栄(参議院司法委員会、昭和22年8月13日)
このように制度設計に際しては、とにかく天皇に累が及ばぬように注意が払われた。今まで首相が告訴に踏み切った実例はないが、それも「かえって皇室にいらざる迷惑の及ぶ」事態を恐れるがゆえのことである。
■旧宮家から来た「天皇の父親」はバッシングの対象になりやすい
このような観点から考えると、当然「天皇の極く身近の方」に含まれるはずの父親を一般皇族とし、告訴権を認めることになれば、刑法第232条の意義がかなり薄れてしまうといわざるをえない。
一親等であっても皇太子以外の皇子は自ら告訴せねばならないのだから、それと同様に特別扱いは不要だ――そう考える者もいるかもしれないが、昭和22(1947)年の片山哲首相の国会答弁では、皇太后を特別扱いする理由として「尊属」であることが挙げられている。
「やはり天皇の尊属である皇太后、あるいはきわめて緊密な関係をおもちになつておられる一家族の方々に対しましては、天皇を象徴たりと考えるということから演繹いたしまして、国民の尊敬を受けなければならない」――片山哲首相(衆議院司法委員会、昭和22年9月20日)
その続柄からして世間的な注目度が高くなることはほぼ間違いなく、必然的にバッシングの対象にもなりやすいはずだから、天皇の直系尊属だというだけでも法的保護を与える――同時に行動を制約することになる――理由として十分だろう。
今のところ一般皇族が自ら告訴なさった事例もないが、あくまでも「御本人のお気持ちで決まること」である以上、今後も絶対にないと楽観してはならない。SNSが普及した現代社会は、昔とは比較にならぬほど手軽に誹謗中傷できるようになってしまっている――という点も考慮すべきだ。
もしも皇族が告訴をお望みになった場合、宮内庁は必死にご再考を促すだろうけれども、無理に抑え込むことはできまい。だからこそ、少なくとも皇父にはその自由を認めるべきではないのである。
■天皇の父親に「太上天皇」の尊号を
天皇の父親に関する不安点を挙げたが、具体的にどうすれば改善できるだろうか。
一般皇族とされる限りは特別待遇を理由付けられそうにないから、何らかの特殊身分を認めるべきだろう。筆者としては、古代以来の「太上天皇」の尊号を贈るのがよいと考える。
太上天皇は、退位した天皇のための称号であるが、天皇の父兄や帝位を諦めた皇族に対して、栄誉として贈られることもあった。ただちに返上されたとはいえ、臣下にすぎない足利義満に追贈された例さえある(※通称「鹿苑院太上天皇」)。
この尊号を贈られた皇父には、後堀河天皇の父親である守貞親王や、先述の貞成親王――ただし、父子揃って後小松天皇の猶子となっていたため、後花園天皇の「兄」として尊号宣下を受けた――などがいる。
太上天皇は「天皇」という用語を含んでいるので、天皇が在位中の方と2人いるようなイメージを与え、二重権威となることが懸念される――。
平成末期に退位後の称号を決める際、そんな意見が多数を占めたことから元々は太上天皇の略称だった「上皇」が正式採用されたという経緯がある。しかし、皇族にも贈られてきた歴史を踏まえると、むしろ皇父には太上天皇こそが適切であろう。
退位特例法における上皇の称号は、字義的意味をあまり意識されないことも多い歴史的称号とは異なり、退位なさる天皇のために創設されたことが誰の目にも明らかだ。ゆえに、もしもそれが皇父にも適用されるとしたら、元天皇と同程度の権威を持たせることにつながりかねないと思うのである。
■近しいご親族には一定水準の立場を保障すべき
ここまで皇籍復帰者が天皇の父親となられる場合にのみフォーカスを当ててきたけれども、直系尊属の扱いが懸念される状況は他にもあろう。
平成から令和への御代替わりが「次第に進む身体の衰え」への上皇陛下のご懸念から実現した以上は、同じようにご高齢となられた皇嗣の即位辞退も許容されて然るべきだ。それは当然、皇父が現れる理由になりうる。
既述のように一般皇族とされうる天皇の母親に関しても、もちろん同様に考慮が払われるべきである。
明治20(1887)年に元老院議官・柳原前光(さきみつ)が起草した『皇室法典初稿』には、「皇族ノ子即位スル時ハ其父ヘ太上天皇ノ号ヲ追尊シ、又ハ現存中之ヲ奉スル」という規定とともに「母ヲ皇太后、祖母ヲ太皇太后」とする規定があった(※第4条、第6条)。この方向性で不都合はないはずだ。
親に尊称を贈ることは、東アジア的な慣習であってヨーロッパの君主制ではみられないものなので、文明開化の一環として廃止されたのだろう。しかし、結局のところ今の在り方は、日本の国柄には合わないように思われる。
特に皇父の場合、特別扱いを一切受けていない方は、飛鳥時代にまで遡らなければ先例がない。自身の父親をそれほどの歴史的例外に置かねばならないとすれば、時の天皇もきっと心苦しくお思いになるであろう。
皇太子以外のどなたが即位なさろうとも、最も近しいご親族は常に一定水準の立場を保障される――そんな仕組みを確立させねば、たとえ十分な皇族数確保に至ったとしても「安定的な皇位継承」を本当に実現できたとはいえないのではないだろうか。
----------
皇室・王室ウオッチャー
日本の皇室やイギリス王室をはじめ、君主制、古今東西の王侯貴族、君主主義者などに関する記事を執筆している。歴史上でもっとも好きな君主は、オーストリア皇帝カール1世(1887~1922)。
----------

 |
エレクトロ
天皇家の血をひく男系男子の養子を女系王家に婿入りした王配を例に話すって根本から間違えてない?お子様が天皇に即位される可能性から来る敬称もわざと混乱を招くような敬称を薦めてる気がするんだけど。 |
 |
spooky
既に皇籍離脱した人やその子孫を皇族に仕立てるの感心せんね、それこそ別の天皇と別の日本国を好き放題にでっち上げることが出来てしまうからな、万世一系とまでは言わぬが常に皇室は一つでなければならない |