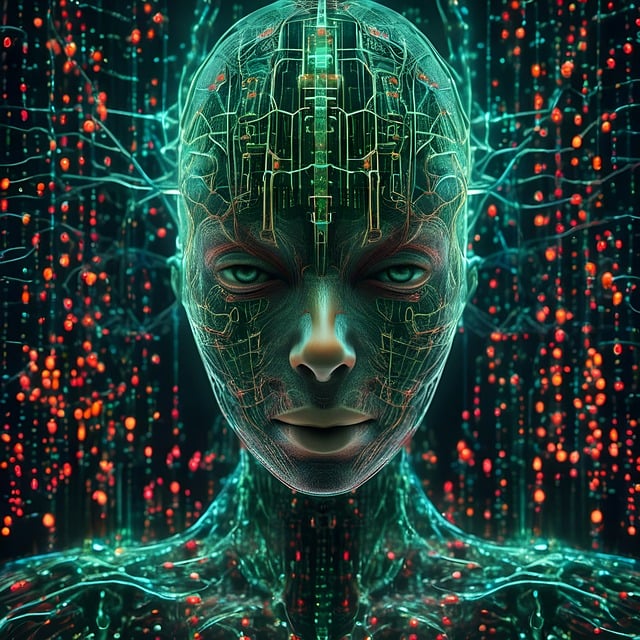|
農家(のうか、英語: Farmer)とは、農業を家業としている世帯や、その家屋のこと。農民、百姓などともいう。農家の定義は、時代や地域によって変わってくる。 農家とは農業(農耕)によって生計を立てている人、あるいはその家庭・共同体のことである。農家が栽培する植物のことを農産物(または農作物)という。…
18キロバイト (1,848 語) - 2025年5月24日 (土) 01:17
|
1. 初年度の厳しい現実
しかし、農業1年目で直面したのは衝撃的な現実でした。
年収はわずか15万円。
それは、以前に祖父が近隣の知人を雇用していた際に支払っていたアルバイト代に過ぎませんでした。
筆者が農業に従事することで、祖父はこのアルバイト代を筆者の収入に転用することができました。
しかし、それだけでは生活は厳しく、販路拡大や独自の収入増を目指す必要がありました。
初年度の収入を向上させるために、筆者はSNSを活用することを決めました。
この近代的なアプローチは、他の成功例、例えば「まいひめ物語」のトマトジュース販売などを参考にしています。
SNSは販路を広げ、商品を直接消費者に届けるための有効な手段です。
筆者もSNSでの情報発信を通じてフォロワーを獲得し、広告収入を得る道を見出しました。
特にSNSの力を借りて、家庭教師の計画を断念し、広告や案件での収入を基に農業ビジネスを展開することを選びました。
また、筆者は新規農業従事者を支援するための補助金制度も受け入れました。
2024年には、合計95万円の補助金を受け取りましたが、この支援がなければ収入はさらに厳しいものとなっていました。
補助金に対する意見は様々で、支援に頼らない自主独立の姿勢を求める声もありますが、筆者の家ではこの支援を活用しながら、今後の農業の可能性に挑戦しています。
現実は厳しいですが、挑戦を続ける熱意は失われていません。
2. SNSを使った販路拡大の試み
この農家は、「まいひめ物語」という名前で高糖度トマトを育て、それを用いた添加物不使用のトマトジュースをSNSを通じて販売しています。特に注目すべきは、そのトマトジュースが季節限定で1本6000円で販売されるにもかかわらず、瞬く間に完売するという事実です。これは彼らのSNS活動が成功していることを示しています。
この成功事例を参考にし、自身の農業活動にSNSを採用した農家がいます。彼はその結果、約10万人のフォロワーを獲得し、SNSを通じての販路拡大に成功しました。そして、フォロワー数が増えたことで広告収入の可能性も広がり、家庭教師としての副業をやめ、農業に専念する決断をしました。
このように、SNSを活用することで、農業の可能性はますます広がります。販路を広げるだけでなく、消費者との距離を縮めることもでき、より多くの人々に自分の農産物を知ってもらうことが可能です。また、フォロワーが多いことで企業からの広告依頼も期待できるため、農業以外の部分でも収入を得る手段となります。
3. 学びと収入の両立
しかし、SNSを活用することで、事態は一転しました。
1ヶ月間で10万人以上のフォロワーを獲得できた結果、広告収入や案件から予想以上の収入源が見込める状況になり、家庭教師としての計画を断念することにしました。
その代わり、農業に専念する道を選びました。
この選択の背景には、SNS成功による新たな収入機会があったことはもちろん、農業自体への情熱が深く関係しています。
SNSを通じて農業の実態や魅力を広めながら、販路を広げることができると感じたのです。
また、農業を通じて地域や人々とのつながりが深まり、自身の成長へとつながることを実感しました。
たとえば、SNSを参考にした先輩農家の成功事例を自らのビジネスに持ち込むことで、新たな販路を開拓したり、農業の持続可能性を高めたりすることに役立ちました。
補助金の獲得もまた大きな助けとなっています。
新規の農業従事者への支援や産業の6次化を目指す取り組みへの補助金で、年間95万円を受け取ることができ、これが農業に専念する大きな支えとなっています。
批判の声もある中で、自らの意志で選んだ道を信じ、必要な支援を活用しつつ、少しずつ前進しています。
農業と広告収入の両立を通じて、私は学び続け、収入を確保しながら、新たな価値を創造することの重要性を学びました。
4. 補助金の利用とその意見
県や町から提供されるこれらの補助金は、特に新規の農業従事者にとって大変貴重な支えとなります。
例えば、私たちが受け取った補助金の中には、県からの新規農業従事者支援として年間75万円のものがありました。
また、6次産業化を推進する町の補助金として20万円も受け取りました。
これにより、合計95万円の支援を受けることができました。
補助金には非常に多くの種類が存在し、それぞれ条件が異なりますが、条件が厳しいものも多いです。
例えば、世帯年収によってフィルタリングが行われる場合もあります。
このような補助金に対して、世間ではさまざまな意見があります。
補助金を利用することは、しばしば他人の税金で成り立っていると批判されることもあります。
「自分の力でやるべきだ」という意見も聞かれます。
しかし、補助金を活用することは、特に小規模な農業経営者にとっては大きな助けです。
わが家の場合も、こういった補助金のおかげで農業を続けることができています。
使えるものは賢く使いながら、将来的には補助金に依存せずに経営を立ち行かせられるよう、努力していくことが大切だと考えています。
5. 最後に
その中で、販路を拡大するためにSNSを活用しました。SNSの活用は農業ビジネスにおいて非常に重要です。例えば、熊本のトマト農家「まいひめおじさん」の成功例を参考にし、私もSNSで農業の実態を発信しました。そして、おかげさまで1カ月後には約10万人のフォロワーを獲得することができ、広告収入も得られるようになったため、家庭教師として働く計画はなくすことにしました。
また、農業収入だけに頼らず、県からの補助金や六次産業化の補助金を利用することにしました。補助金は利用できるものはしっかり活用する方針です。中には、補助金を受け取ることに対して厳しい意見もありますが、短期的には経営の安定が最優先だと考えています。
農業収入が低い今、補助金は大きな助けとなっています。しかし、将来的には販路拡大やSNSの活用をさらに進め、補助金に依存しない経営を目指していきたいと思います。農業の初年度を通じ、この業界の厳しさと可能性の両方を痛感した一年でした。これからも挑戦を続け、自立した農業経営を実現したいと考えています。